2025年8月5日
10:22
広島へ向かう上空。快晴。
おだやかな気持ちと、少しの不安。
14:28
原爆ドームを見学。昼間の原爆ドームをじっくり見るのははじめてだった。いつも広島を訪れると見にくるけど、決まって夜。人が少なく、原爆ドームと自分の二人だけみたいな気持ちになれるから。夜はライトアップもされて、少し怖いけど幻想的。
今日は8月5日ということもあって人で溢れている。外国の方も多い。集まった人たちの様子も見ながら、犠牲になった学徒の慰霊碑をお参り。
晴天の下これだけ多くの人たちが集まっているが、もちろん祝祭などではなく、笑い声もない。どこか不思議な空気。祈りに近い、あたたかい静けさを感じる。
移動。
原爆の被害に遭い家を失った人たちが暮らしていた集合住宅を通過。かつては原爆スラムと呼ばれていたらしい。中には学校もあり、一つの巨大な街と化していたエリア。
今では多くの人がこの場所を離れ、住んでいる人は少数とのこと。新しくできたサッカースタジアムも通過。とても立派。
17:55
被爆経験者である梶矢さんのご自宅に行き面会、その後、資料館見学。あっという間。
濃密な時間だった。
86歳の梶矢さん、奥様が亡くなられ今は一人ご自宅で生活されていた。足取りもお話もしっかりされていてとてもお元気、生気に満ちていた。何より、力のある眼が印象的だった。熱をもって被爆した当時の話をしてくれた。
1945年8月6日朝、爆心地から1.8キロのところにある学童所で掃除をしている時に被爆。当時6歳だった。
本人は玄関、お姉さんは居間の雑巾がけをそれぞれしていた。突然ピカっという閃光、ちょっとしてからドンというものすごい轟音と振動、そして衝撃、風圧。たまたま玄関にいた梶矢さんは柱に守られ助かった。お姉さんは倒れてきた建物に押し潰され亡くなった。
家屋に押し倒された時何が起きているのか分からなかった、と。ただ上を見ると瓦礫の隙間から微かに太陽の光が見えた。そこを目指して力を振り絞り、瓦礫や柱やガラスを掻き分けなんとか上へと這いのぼる。傷だらけの身体。室内にいたことで直接の熱波は避けることができた。周りの家屋や建物は全壊。家の前には無数の人の列。「じき火事になる」と、皆が急いで避難をしている。6歳の梶矢さん、どうすればいいかわからずその列についていく。二葉山に避難する。数時間すると市内は火の海となる。山の上から街を見下ろす梶矢さん。その恐ろしさを想像する。真っ赤に燃える、街、家、人。
お母様の話をされている時が印象的だった。
自宅で被爆した母は爆風により飛んできた無数のガラスにより負傷。全身に何十箇所と刺さったガラスを父親が抜いてあげる姿を覚えている、と。左目にも刺さったガラス。麻酔もない。それを抜く父の姿を想像する。左目はその怪我により失明した。ガラスで母の顔面に深く刻まれた傷跡。
しばらくして梶矢さんは中学にあがる。授業参観で教室の後ろから見ていた母親を同級生の子供に「誰だあの化け物」とからかわれた。母に、もう学校には来ないでと伝えた梶矢さん。あの時は悪いことをしたなと思った、と語った。話をする梶矢さんの眼には涙が浮かんでいるように見えた。
胸が苦しくなった。苦しかった。
家族を奪われ、傷つけられ、アメリカ、敵国に対して憎しみが湧いたか、と質問してみた。アメリカに対してそれほど憎しみを抱かなかったと言ったのが意外だった。むしろ「負けた相手がアメリカでよかった」と梶矢さんは言った。
僕は知らなかったが敗戦に向かう当時の日本を4つに分断し、それぞれ違う国が統治する案があったらしい。詳細は忘れてしまったが「北海道・東北」をロシア、「関東・関西」をアメリカ、「九州」をイギリス、「四国」を中国といった具合に。ドイツがちょうど東西に分断し、別々の勢力が支配したように。それよりはアメリカ一国に統治されたほうがよかったと言っていた。この国にそんな歴史の分かれ道があったことをはじめて知った。
8月6日被爆した後、荒れ果てた市内を離れ山の方に住む親類の家にお世話になった梶矢さん一家。原爆投下直後、被爆した人への差別や偏見はまたたく間に広がり親類からも特異な眼で見られることとなる。自分たち家族は親類家族のいる母屋とは離れた部屋に隔離され生活したとのこと。そこからしばらく、「被爆者」として生活を送ることとなる。
長年、被爆経験者として自分は子供を作っていいのだろうか、子孫を残していいのだろうかという苦悩、もがきがあったと言っていた。
二十歳の時、原爆資料館で「被爆しても子供への遺伝的影響はない」と書かれた文言をはじめて見た時、しばらくその前で立ち尽くして動けなかったと言った。
「自分は子供を作ってもいいんだ」そう思えた時の気持ちを想像する。聞いている僕も、込み上げるものがあった。梶矢さんには現在二人のお子さんがいて、今もお盆と正月にはそれぞれ家族を連れて会いにきてくれるらしい。
被爆体験とは関係ないけれど、最初梶矢さんのご自宅にお邪魔した時、居間に遺影が飾られていて「奥様ですか?」と尋ねた。
「うん、亡くなってから7、8年になるかな。乳ガンで一度手術をして、5年再発しなければ大丈夫と言われておったんだがダメじゃった。5年目に再発し、その3年後に亡くなった」とおっしゃっていた。
ただ、死ぬ直前「ありがとう」と言ってもらえて救われたと言っていた。
「あんたと一緒にならなければよかった」「なんで私がこんな目に…」とか、何か文句を言われて死なれたら残された方は一生後悔し、心が休まらないと言っていた。確かにそうだなと思った。最期の言葉って、最後じゃないんだなと思った。誰かの中にはずっと残って、そしてまったく見ず知らずの東京から来たこんな僕の中にも、今残っている。
「ありがとう」と言って終われる人生を僕も生きたい。
広島平和記念資料館
何年ぶりかの来館。2019年にリニューアルされたということで、たしかに展示は大きく変わっていた。より原爆投下当時の実物、実際の写真の展示に重きを置いた内容になったとのこと。
今日は8月5日ということで中は超満員。とてもじっくり見れる様子ではなかったので、ツアーの時に改めて再訪してしっかり見ようと思った。
アメリカの人がとても多かったのが印象的だった。ヨーロッパ系の白人ではなく、アメリカの白人(長くアメリカに住んだので違いがよくわかる)。
この8月6日に向けて訪れる原爆投下当事国の人たち。こんな言い方はおかしいと思うが、ありがたいなと思った。自らの足で、自分の祖国がした行為が他国の人々にどんな影響を与えたのかを深く知ろうと、遠い国まで赴く。簡単なことではないと思った。
昨年資料館を訪れた人は200万人を超え、3割が外国の人だった。この資料館を訪れる人が増え続けていること、核そのものが年々増え続ける中でこの事実は小さくとも紛れもない希望だと思った。
館内に多数展示された写真。荒廃した市内、無数に散らばる死体、ケロイドまみれの背中、判別つかなくなった顔、治療を受ける子供。
写真というメディアの偉大さを知る。
どんな気持ちでシャッターを切ったのだろうか。そんなことを思う。目の前で悲嘆にくれる人、命果て亡骸となった遺体を前に、手を差し伸べるでも手を合わせるでもなく、シャッターを切る。心が張り裂けそうになる想いを想像する。
それでも「なんとかして残さなくては」という叫びみたいなものを感じる。執念。フィルムに焼きついた念、願い。ちゃんと「80年後の僕たちは受け取りました」そう言いたくなる。
じっくりと館内を見ることは叶わなかったが一つ、はじめて目にする資料があった。1945年7月20日から、実に49発の原爆の模擬爆弾が日本各地に投下されていた。大阪、神戸をはじめ名古屋、浜松、富山、西東京、長岡など広範囲に及び、それだけでも1600人以上の死傷者を出した。
その地域の中から7月25日広島、長崎、小倉、新潟の4都市に絞られた。
実に周到に練られ、準備された原爆投下だった。
ふと思う。
人間とは本来、戦うものであり、争いが避けられないものであり、奪い合うのが定石なんだとしたら。放っておいても戦う生き物なのだとしたら、なおさら難しい方を選びたい。
誰にでもできることではなく、簡単な方ではなく、平和を選びたい。せっかく生まれてきたのだから、僕らにしかできない方を選びたい。
そんなことを思った。
8月6日
7:26
広島原爆の日。晴れ。久々の5時起き。
地元の人に聞くと広島のこの日は晴れることが多いと言っていた。80年前の今日、天気のよさも大きな一因となり原爆投下は決行されたと聞いた。
再び原爆ドーム前へ。昨日とは様子が違う。デモ隊、警察、機動隊の群れ。人、人、人で溢れかえっている。拡声器で「戦争反対」「トランプ政権反対」の大号令。無数の旗、プラカード。異様な空気。どこか鎮魂の気持ちを胸に朝を迎えた自分には、唐突で、凶暴に見えた。同時に、人々の切実な想いなのだとも思った。
大勢の警察官や機動隊、皆長袖に防弾ベスト、重装備。とんでもない暑さの中、大変そう。
9:08
式典終了。式典自体に何か特別な感慨は沸かなかった。会場自体も離れていてスピーチの声もよく聞こえなかった。来賓、総理の、どこか形式ばった挨拶に聞こえた。
※後から全員のスピーチを文章で読んだ。広島県知事の言葉には熱量がこもり、切実な願いが溢れていた。四方八方に忖度していては誰にも届かない。伝えなくてはいけないという気概を感じた。
8月6日、午前8時15分。この時間に、この地で黙祷を捧げることができた。
この事実が、自分にとって一番大きなことだった。
「平和の灯」を、はじめて目にした。一年中絶やさずその炎は燃え続ける。その周りには水を張った池。どれだけ渇水になろうとその水は絶やさないようになっているらしい。原爆投下後、人々が水を求めて彷徨ったことからこのような造りにしたそうだ。
「地球から核がなくなった時、はじめてその平和の灯の炎は消される」とのこと。美しい目標だなと思ったと同時に、その日までの道のりの遠さにどこか悲しさを覚えた。
まだ自分には現実味のない願いのように聞こえた。少しでもそこに近づけるように何ができるのだろう。何ができるんだろう。
長い挨拶の間(じっとしていてもよく聞こえないので)、平和記念公園内を散策した。
韓国人被爆者の碑、引き取り手のない遺骨を納めた原爆供養塔をまわり、手を合わせお参りをした。
20万人といわれる原爆犠牲者のうち、広島では2万人もの韓国人犠牲者がいたことが衝撃だった。全体の10%。あまり語られることのない事実。もっともっと多くの人が知るべき事実だと思う。
式典が終わり、帰りがけ僕のことに気がついた地元の高校生たちが走ってきて、9時から佐々木禎子さんの紙芝居をやるから見て行ってほしいと声をかけてきた。残念ながら次の行程があるので丁重にお断り。声をかけてくれた女の子は合唱コンクールで「正解」を歌って優勝をしたらしい。嬉しかった。
式典スピーチの中にあった言葉で印象的だった数字。
「世界の核の9割をアメリカとロシアが保持している」らしい。
そんな単純な図式ではないにせよ全校生徒数百人いる学校で力のあるたった二人のケンカにみんなが巻き込まれていくような変な気持ち。「お前はどっちの側につくんだ」そんな勢力争いが繰り返される。両者ともに力があり弁も立つ。
中庸はなくなり、二者択一を迫られる。
大半の力を極小数の人たちが独占するという意味で世界の富の75%を世界の上位10%の人が持っているという事実にも似ていると思った。
支配する側、される側。
核もお金も、一度手にした人は他人には決して持たせたくないのだ。そして自分のは絶対に手離したくないのだ。人間は悲しいかな、そういうふうにできているらしい。
自分たちで到底扱いきれないものを生み出した人類の末路は、どんなものなんだろう。
なんだろ、この説明の難しい、そこはかとない苛立たしさは。
どこか形骸化していく挨拶。戦争において核を落とした世界一の核保有国、アメリカ。その傘に守られ続け、防衛、外交、あらゆる面で言いなりになる日本。
核廃絶を訴える声、声。切実なる声。一方で毎年着実に、この地球に増え続ける核。嘲笑われているような気になってくる。
誰かの願いを踏みにじる足。
全人類が「悪」と容易に判断できる凶器を、迷いもなく手にしたいと願う支配者たちの狂気。その支配者の中にも堂々と存在する「正義」。
地獄みたいだ。
平和とは、戦争と戦争の間に生まれる、ほんの気休めのような小休止なのだろうか。奇跡のような、ご褒美のような、休息なのだろうか。
そうやって「平和ボケ」した人類は性懲りもなくまた何事もなかったかのように争いへと向かうのだろうか。
人類はどうやらそれを繰り返し続けているらしい。何千年と。
この先の未来、何千年、何万年とそれを繰り返すのだろうか。そんなことを繰り返して、地球は果たして耐えられるのだろうか。
ノアの方舟はもうやってくる気がしない。
かつて1979年、NATO諸国に中距離核弾道ミサイルが配備されヨーロッパやアメリカで大規模な反核運動が高まり、1982年3月、広島で行われた「平和のためのヒロシマ行動」では約20万人が平和記念公園に集まった。本気で核をなくしたいという人々の願いが集結した。確かに、当時は70,000発あった全世界の核兵器。確実に減少はしてきている。ただこれを失くす、ということの難しさも痛感する。「ゼロ」にする難しさ。
拳銃を向け合っている者達同士が、拳銃を下に置く瞬間。しかもそれが何人もいる。下に置いたとして、まだ相手は胸ポケットにもう一つ隠してる可能性もある。「これで全部だ」どうやって相手の言葉を信じる?渦巻く疑心暗鬼。
容易ではない。
12:02
被爆したピアノを見学、そのピアノを管理し調律も行っている矢川さんという方にお話を聞いた。実際のピアノも少し試奏させてもらった。
広島駅からすぐのお宅で被爆したピアノ。長年矢川さんはこのピアノの音色を届けに全国に足を運んでいるとのこと。
今ではとても珍しい象牙でできた鍵盤。鍵盤のサイズも現代のピアノとは微妙に違う。象牙の肌触りはなんともやわらかで、はじめての感覚。今のご時世、絶対に作られることはない。
白鍵はたくさんの人に弾かれたことで茶色く、黄色くくすんでいた。それが愛しいなと思った。歴史だけが出せる色。たくさんの人がこのピアノを弾いてきたのだ。その時の気持ちを想像する。
昭和10年ごろに作られたピアノとのことで現在約90歳。チューニングはやはりピタリと正確というわけにはいかず、どうしても狂ってはいるが嫌な響きはまったくない。人間と一緒。90年経ってまったくの正調なわけがない。ガタがきて、ヨレるのが普通。そんな音色が心地よかった。音の滲み。
戦争、原爆をくぐりぬけ、ちゃんと今も鳴り続けている。その事実だけで充分だと思った。そして僕らの命よりもずっとずっと長く、存在し、この先も人の手によって演奏され続けてほしいと思った。
その後、最後のNHK岡崎さんとのインタビュー。
明後日第二子が産まれるとのこと。そんなタイミングでの広島原爆の日、訪問だったことを知る。
日本は戦後80年。
江戸時代のある時期を除いて、これほど日本の歴史の中で戦争が行われなかった時代はほぼ存在しない。明治維新以降だけでも西南戦争、日清戦争、日露戦争、満州事変、日中戦争、太平洋戦争。日本は戦争ばかり。
トランプ大統領は核によってあの戦争を終わらせられたと言った。アメリカの多くの人がそれを今も信じているのは事実だ。鵜呑みにする気はない。ただ一つ言えるのは、あの時日本は負けたから、この平和を手にしている。戦いのループから降りることができた。あまりに大きな犠牲だったけど、その犠牲を無駄にしたくなんかないと、それだけの痛みと引き換えに手にした平和なら、ちゃんと守りたいと強く思う。
核兵器とはなんだ。
人を殺めてしまうもの。破壊してしまうもの。
抑止力とはなんだ。
相手に特定の行動を思いとどまらせるための力。
核はない方がいいに決まっている。ない方がいいに決まっている。
でも、では、なぜこの国に拳銃はある。
一般市民の中に混ざって、警察は拳銃を所持している。なぜ。
そしてそれを是としている。
核と、拳銃の違いは?
一度に殺せる人の数?
では、なぜこの国にミサイルはある。戦闘機はある。
軍を持たない日本。それでも日本の防衛費は世界で10位に入る。
立派な軍事国家に思えてくる。
なぜあれだけの苦しみを経てもなお、人を殺める武器を持つ。殺戮できる凶器を持つ。
抑止力?
では、なぜ核を否定する。
そんな問いにすら僕はまだ明確な答えがない。
脆く、弱い。
吹き消されそうなほどか弱い自分の正義が、虚しくなる。
でも諦めたくはない、そう思う。
今回、岡崎さんたちの質問に僕はほぼ何一つまともに答えられなかった。とても無力だなと思った。でも、安易な言葉に落とし込むことを自分の本心がすごく嫌った。それだけはよくわかった。まだ言葉にするな、わかった気になるな、すぐ手の届く答えにすがるな。そう自分が自分に言っている気がした。やはり、テレビというメディアで語るには僕は役不足だった。取材を申し込んでもらってとても申し訳ないなと思ったが、自分はこういう人間であり、こんな人間に取材を依頼した岡崎さんたちにも少しは責任があるよと、若干開き直ってみたりする(すいません)。
ただ、この機会を僕にくれて、この日に広島に連れてきてくれて、心からありがとうございました。
野田洋次郎



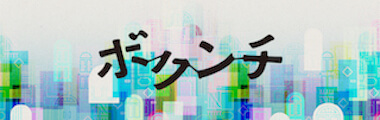
コメント(115)
Arado
玲美
犬助
みさ
ぷう次郎
木暮
はる
もりやはるこ
ys
いちご
服部 愛
瑛心
渡邉利昭
高山美保子
岡崎美紗
小泉
しるく
忍足
美佳
倉知真紀
しょう
かとうふみこ
うらら
阿部まゆ美
りさ
Izabor Rodrigues
えり
鈴木
tomy
木村良美
松田和子
広畑祐人
田村理恵
ほみ
保科 慈
り
井上 真帆
後城麻衣子
石塚 奈緒
たろう
A
Alisamiko
絵里香
石田虹
ピカーッ
永野莉音
後藤 佐恵子
サリー
きよきよ
モリモト
須藤涼音
ありがとう。
みこ
16歳
mi
DADAcco
はな
ひより
mmk445
nori
うえだ真衣
マ
松永 しおり
タケシ
Ajeng
ミキ
賀来 りか
KOSEI
しずく
小笠原理恵
むう
み
酒井 アスカ
ヨシコ
yok
ムラサキ
長坂裕太
ゆうき
景子
星
はるか
石川由紀子
井上 妃世
タニガワミサ
美森
陽永
高橋 菜摘
8maru
瀧野 玲奈
山口 凌叶
岡本千明
ゆうな
三枝早紀
安井悠良
れあ
きんた
坂口洋子
桑原麻友子
亜紀
瀧野
乾
櫻庭弥生(やどん)
りょうすけ
若松 采音
はしもとしずか
西川 桂子
かにまる
安藤有梨
遠藤華子
香保(たこちゃん)
arisa